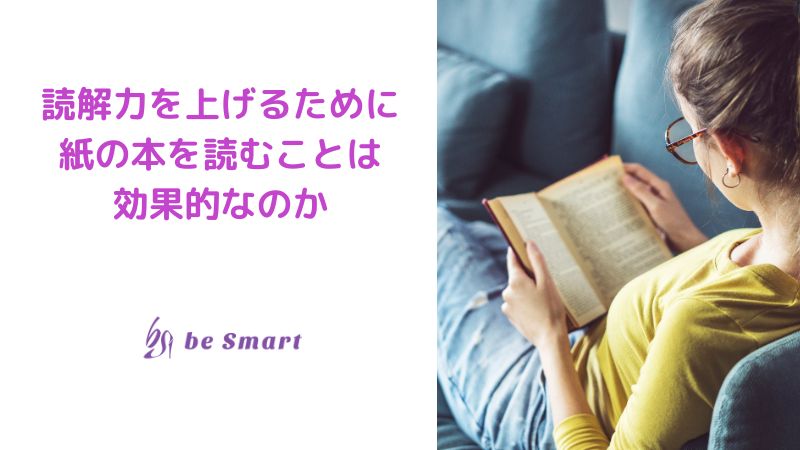大人も子供も読解力が落ちていると言われています。文字を見ることができても読むことができないという状態です。
たとえばお店で「店内のコンセントのご利用はご遠慮ください」と書いてあったら、利用しないのが一般的な捉え方だと思うのですが、「遠慮してください」を「できればやめてほしいけど、どうしてもという場合はいいですよ」みたいに捉える人が一定数存在して、時々SNSを騒がしています。
読解力の低下とともに言われているのが、読書離れ、本離れですね。漫画ばかり見ているということではなく、ネットで動画を見るようになったということです。あなた自身はいかがでしょうか。周りの人はどうですか。
この読解力の低下と読書離れはセットで語られやすいですし、私もそう思っていたのですが、「果たしてそれはイコールなのか」と考えさせられる機会がありました。それは1つの動画なのですが、最後にはっておきますので、ぜひ見てみてください。
この記事では、読解力と読書について私の個人的な考えを述べたいと思います。
読解力とは何か
学生時代に「長文読解」があったことから、読解力=長い文章を読んで理解することだと思いがちですが、文科省ではこのように定義されています。
自らの目標を達成し,自らの知識と可能性を発達させ,効果的に社会に参加するために,書かれたテキストを理解し,利用し,熟考する能力。(文部科学省より)
文章の長さにかかわらず(「ご遠慮ください」が理解できないってことはそういうこと!)、“理解”したり、“熟慮”したりできるかってことです。
例えば「この本にはなんて書いてあった?」という質問は、一字一句どんな言葉が書かれていたかを聞いているのではなく、要はどういうことが書いてあったのかテーマや結論を教えてということですよね。
私は過去に読解力をテーマにした記事を書いておりますので、こちらもお読みいただけると嬉しいです。


このブログにたどり着いてくださったのなら、日本人が全体的に読解力が落ちているというのは見聞きしたり、肌で感じたりされているのかなとは思いますが、そのことと「読書をしないこと」はイコールなのでしょうか。
最後に載せていますが、ある動画を見るまでは私はそう思ってました。
ですが、「イコールではないのかもしれない」と考えが変わった感覚が私の中であります。もう少し丁寧に言うと、次のとおりです。
- 本を読むことで読解力はつく
- 読解力をつけるために本を読むことは推奨する
- 本を読まなければ必ずしも読解力が上がらないとは言い切れない
つまり、本を読むことはとても推奨するし、読解力以外の様々な力もつくと思うけれど、本を読まなくても読解力を身につける方法はある、と思ったのです。
読書感想文で受賞したときの話
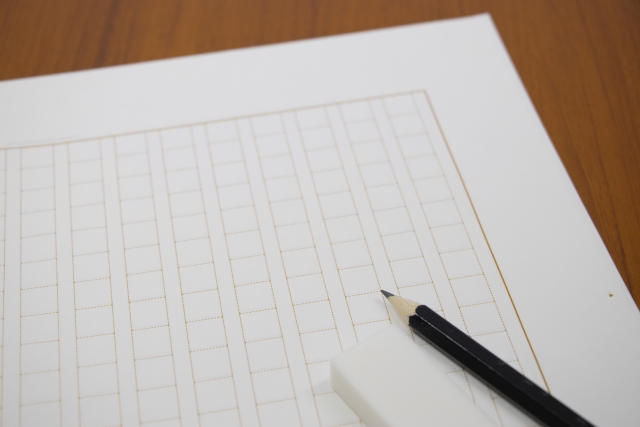
私は小学6年生のときに、夏休みの宿題「読書感想文」で賞をもらいました。
もともと文章を書くことは好きだった記憶があるのですが、6年生の夏休みに自ら本屋さんで「読書感想文の書き方」なる本を購入したんですね。原稿用紙何枚以上というルールがあって、長いなぁ~何を書いたらいいのかなぁというのはおそらく年々感じていたので、どうしたらうまく書けるかというより「結局、何を書いたらいいんだ?」を解消すべく購入したんですが、これで目の付け所がわかったのは大きかったです。もちろん小学生レベルではありますが。
その後、地元の公立中学、高校は公立の進学校に進むのですが、「英語が楽しくて仕方ない反面、国語の点数がそれほど取れない」を目の当たりにします。日本語なのに、なぜこんなにテストの点がとれないのかわからなかったので、克服の仕方もわからなかったのですが、大学進学を見据えたときに「このままではやばい」と、参考書を買って学び直しました。
振り返って思うのが、私は読解力がなかったんですね。国語のテスト問題を、ちょっと自分の思い込みを入れて読んでしまっていたんです。
例えば「作者はどのように感じたか」という問いがあったとして、それは必ず文章中に答えがあるのですが、高校生の私は「こう思ったに違いない!」と“想像”して書いていたんです。読書感想文は私が思ったことを自由に書いていいのですが、作者の気持ちは私の気持ちではありません。ごっちゃにしてはいけないんです。
大人も社会の中でこういうことってありませんか。
あなたはどう思う?に対して、世間の声を言ってしまったり、アンケートの結果をまとめる際に自分の考えを盛り込んでしまったり、日常的なところでいうと、看板やアナウンスの注意喚起も「でも自分は関係ない」としてしまっていないでしょうか。
読解力がない人というのは、そこに余計な思い込みを入れてしまっていませんでしょうか。
読書量と読解力
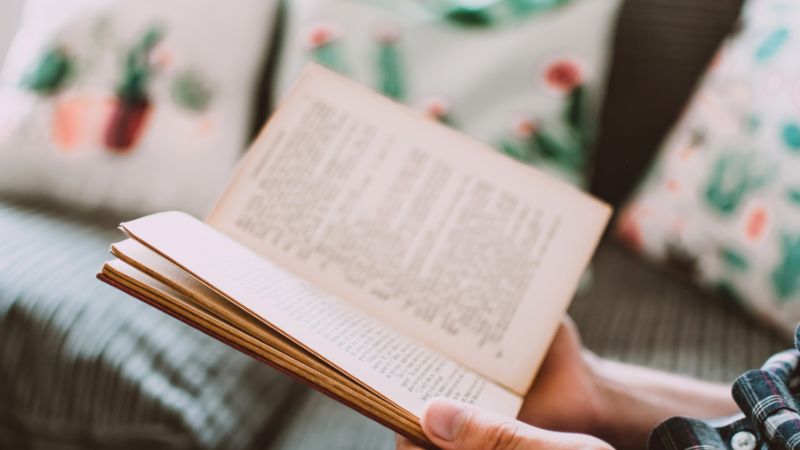
2024年に厚生労働省の一般職業適性検査でIQを調べてみたところ、私は言語IQが150を超えていました。(ちなみに空間把握能力は低かった…よくこれでステージで踊ったりできていたなぁと思っています)
言語IQは、些細な違いに気づける力があるとも言われていて、決して語学堪能とか、そういう数値ではありません。それでも今の私は読解力はある方だと思っていて、周りの方(特に年齢やキャリアが上の方)から、「麻紀さんは1言えば5も10も理解してくれるから助かる」とよく言ってもらえています。
じゃあ、私はよく本を読んできたのか(読んでいるのか)というと、そうでもありません。
全く読んでいない層ではありませんが、「よく読んでいる層」では決してないのです。
では、私の人生の中で読解力に結びつきそうなことを思い返してみると、次の2点に落ち着きます。
読解力に繋がったかもしれない2点
さほど本を読んで来なかった私がなぜ読解力を身につけることができたのか、思い返してみました。
舞台役者の経験
20代から30代の約10年間、舞台役者として活動していました。
ご想像通り、役者は台本を読んで理解し、それを現実世界に再現します。ト書きといって、台詞以外の説明文もあるのですが、誰がどこに立ってどういう動きをして、どんな表情をして、どのようにしゃべるかと事細かには書いてありません。演出家とともに役者たちがコミュニケーションをとって、「ただの文字」から世界を作り上げていきます。
このときに読解力がなければ、台詞を覚えたとて役として生きられないので、お芝居はできません。読解力とともに想像力もかなり鍛えられたと思います。
意図を読む

なぜ相手がそう言うのかを、言葉(表面:聞こえる部分)だけでなく、その奥の背景や意図を読もうとしているのかもしれませんが、かなり無意識でやっています。意図を読む=読解力がある、と言ってしまえばそれまでですが、意図を読むときは相手の言葉や文字に限った話ではありません。
混雑したカフェのテーブルに誰かがハンカチを置いていたら、忘れ物だとは思わないですよね(可能性はゼロではないですが)。席を確保しているんだなと、ハンカチの持ち主に聞かなくとも、その行動の意図を読むことができます。
自分という主体が常に頭の真ん中にいると難しいですが、自分の考えや価値観は横に置いといて、目の前にいる人がこう言っているという事実だけを受け止め、その発言の中に私を含めていないのです。(伝わりますか?うまく言えないな~~)客観的に聞くことに徹底しているので、自分の価値観というフィルターや思い込みをなるべくかけないというか…。
まさに国語のテストのようで、「作者は何をし、その結果どう感じたか」を、目の前の話し手に置き換えているだけで、私のこと(人生経験、価値観、趣味嗜好など)を極力挟まずに聞くことを意識しています。
こういうふうに人の話を聞くと、「それはわかるし共感もする」と「それはわかるけど共感できない」という2つの感情がわきますが、他人の話で自分がかかわらないことであれば、わざわざ共感できるかどうかを自分の中でジャッジする必要はなく、ただただ相手の話を理解しただけになるのでネガティブな気持ちはわきません。
「反対意見」には2種類ある
例えば有名人の発言がSNSをざわつかせるとします。ざわつくというのは「それっておかしい」という反対の声があるからですが、この反対の中には「共感できない派」と「そもそも発言を理解していない派」がいると思っています。
前者は読解力があり、相手の主張を理解しているが、「私はそうは思わない」と言っているだけなので、こういう人がいることで議論が活発化していきます。悪い存在ではないと思っています。
そもそも発言の意図を理解していない人たちは、理路整然と反対意見を言うことができないので、途中から「でもみんんな困っている」みたいに急に主語を大きくし、何かの代表気取りになります。
読解力を高めるために
読解力という能力を身につけるためには、読書だけが唯一の方法ではないなと思ってきました。
とはいえ、紙の本はきちんと校正されているので美しい(正しい)日本語ですし、映像がなく活字だけの世界に没頭することで想像力を養うことはできるので、『読書はした方がいい』に私は一票入れたいと思います。
私自身の経験から、読解力は想像力や論理的思考力も必要かなと思い始めてきて、そのためにはなるべくいろいろな人と出会い、様々な価値観に触れておくことは、ひとつの方法ではないでしょうか。それで本というのは他人が書いたものであったり、小説だといろんな登場人物が出てきたりするので、疑似体験として有効かなという考えです。
ちなみに私は、演劇経験を用いたコミュニケーション力を養うワークショップを行ったのですが、これが好評でして、読解力にも繋がると思っています。
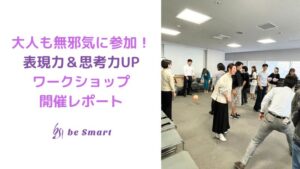
こちらのワークショップは、協会として立ち上げ、今後もワークショップを開催していきますので、ぜひこちらをチェックしておいてください。
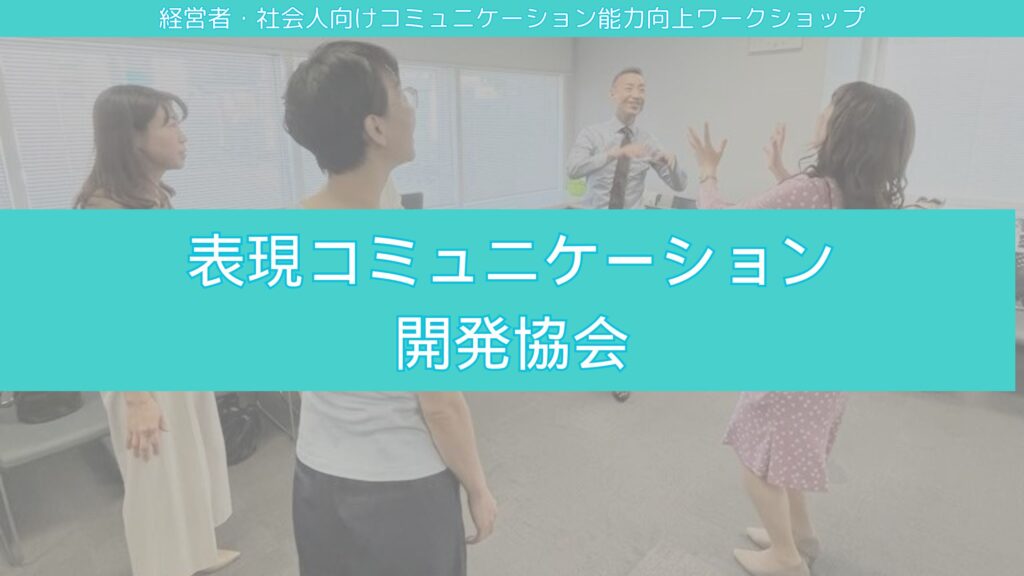
気づきを得た動画の紹介
では最後に、私が「読解力=読書」は本当かと、ふと足を止めた動画を紹介致します。
ビジネスをしている方はぜひ見ていただけたらと思います。(ちなみに私は読解力向上以外にも理由があって、動画内でプレゼンされるサービスに私は賛成です)