いつもは「話し方」に焦点を当てて記事を書いておりますが、今日は「書き方」に触れたいと思います。
 坂本
坂本書くということも表現ですし、話すと同様に言葉を使うことには変わりありません。
人とのやり取りも、電話でしゃべるより、メールやチャットを使ったテキストでのやり取りが主流ですから、「書く」という表現方法も改めて磨いていきましょう。
話し言葉と書き言葉が与える印象


まずは話し言葉と書き言葉の違いを認識し、それぞれにあった言葉を選ぶことで、よりスマートな印象を与えることができます。
SNSを活用している人はテキスト入力に慣れていると思うのですが、SNS(特に個人ブログや、Twitterやインスタなどのライトな発信)で使われる文言は、主に話し言葉です。
SNSの世界は基本的に話し言葉で表現しているので、親しみやすさを感じやすいのはそのためですね。



ちなみにこのブログもあえて、やや話し言葉寄りで書いています。
同じネット上にあるものでも、会社のホームページやプレスリリース、ライターの原稿などは書き言葉の方がオススメです。
ここで話し言葉(口語)を使うと、幼い印象を与え、信頼性にも影響が出てくるでしょう。
話し言葉と書き言葉の違い
- だんだんと雨足が強くなってきた
- なんで、あっちに行こうとしたのか
- ちゃんと着れると思った
これらはすべて話し言葉です。音読してみても、違和感がないと思います。
では、書き言葉に直してみましょう。
- 徐々に雨足が強くなってきた
- なぜ、あちらに行こうとしたのか
- きちんと着られると思った
きちんとした感じが出てきましたね。
おそらく「見慣れている言葉」であって、「話し慣れている言葉」ではないと思います。
話し言葉と書き言葉の違いでは、
- 接続詞(例:~~なので/~~けど)
- 副詞(例:なんで/たぶん)
が変わることが多いです。
その他にも、上に挙げた「着れると思った」のように『ら抜き言葉』や、「~~していました」ではなく「~~してました」とする『い抜き言葉』も注意が必要です。



Wordを使って文章を書くと、『ら抜き言葉』や『い抜き言葉』には二重線が引かれて教えてくれるので、何を間違ったんだろうと手を止めて見直してみてくださいね。
この辺りのことは、文章を書く上でよく言われることなのですが、私は「書き言葉には熟語を使うのもアリ!」と考えています。
例えば…
- 扉を開閉する(口語:扉を開け閉めする)
- 自作してみる(口語:自分で作ってみる)
- 不明です(口語:明らかになっていません)
話すときにも「挙手をお願いします」「趣味は登山です」「頭痛がする」というように、自然に熟語を使うこともありますよね。
書き言葉は、より無駄がない方がスマートなので、「開け閉めしてください」と書くより、「開閉してください」がシンプルにまとまります。
『温度や湿度が高い場所を避けて、外気温を超えない自然な温度のところで置いておく』という一文ではなく、『高温多湿を避け常温にて保存』と書いてあるのを私たちは見ているはずです。
熟語を使うことで、その字面から瞬時に意味を理解できます。
フォント選び
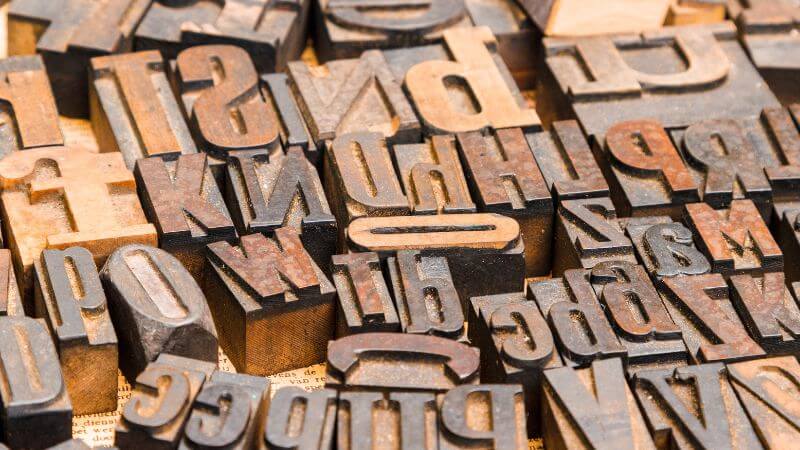
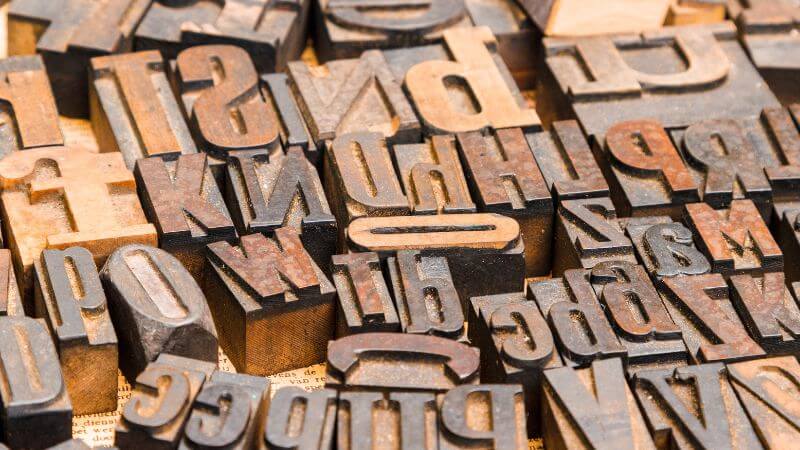
パワポやCanvaを使って資料を作るとき、ついついフォント選びに時間を費やしてしまうことはないでしょうか。
昔、デイサービスで働いている時に、月1回のお便りが本社から送られてきて、デイサービスの利用者様にお配りしながら、一緒に目を通していたことがあります。



例えば1月なら新年の挨拶とか、梅雨の時期には食中毒に注意するとか、夏は熱中症、冬はヒートショックに関する注意喚起などですね。
そのお便りの文章のフォントが、創英角ポップ体だったんですね。
こんな感じです。
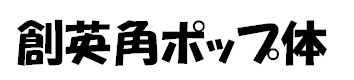
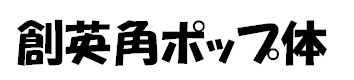



これ、見づらくないですか?
おそらくこのフォントをわざわざ選んだ理由は、太文字の方がはっきり見やすいから、もしかしたらゴシック体よりもちょっと丸みを帯びていた方が親しみやすさを感じられるから…というところではないでしょうか(憶測ですが)。
見出しや強調したい言葉だけならともかく、すべての文章が創英角ポップ体だったので、ご高齢のみなさんからは「読みづらい」「見づらい」と不評でした。
高齢者の方を想定した時に、行間を適度に開けることも大切だと言われているのですが、A4サイズの紙に書いてある本文が創英角ポップ体だと、全体的に黒くなってしまいますから、太めのフォントがいいといっても、サイズや全体の見た目からいって、合っていなかったのですね。
一方で、40代の経営者向けの話し方講座の資料で、オンラインセミナーでお見せするものは明朝体で作成しました。
終わった後に直接いただいたご感想で、「明朝体で書かれているとすっきり読みやすいし、きちんとした感じがより伝わってきました」と言っていただけ、そのまま個別サポートのお申込みにつながりました。
同じくらいの年代の方向けでも、セミナールームでプロジェクターを使って見ていただく資料は、明朝体ではなく、ゴシック体を使いました。
この場合に明朝体だと、線が細くて見づらいこともあるからです。
- 明朝体は『読んでもらう』もの
- ゴシック体は『見てもらう』もの
と認識して使い分けるとよいかと思います。
話し方と同じで、書き方も自分本位で決めるのではなく、読む人の立場になって考えると答えが出てきますね。
話すときにはその声色もデザインすることをお伝えしておりますが、書くときにはフォントや大きさがその役目を果たします。
大きな声でゆっくり話す必要がある人には、大きな文字や、やや間隔を開けた文章が好まれます。
わかりにくい文章とは


メールやチャット機能など、字体を選べないものもありますが、表現方法(書き言葉)を磨けば、決して冷たい印象にはなりません。



良かれと思って、丁寧に書きすぎると、かえって読みづらかったり、要点がわかりづらかったりするので、相手にとっては不快な文章になってしまいます。
わかりにくい文章の代表格は、とにかく一文が長すぎることです。
話すときと違って、途中で息継ぎをすることもなければ、相手が「それってどういうこと?」と割り込んでくることもないので、書き手の頭の中にあることをつらつらと書き並べがちです。
「実はこのようないきさつがあって…」と状況説明をする際に、要点だけを抽出できずに、起こったことや感じたことをすべて書き並べてしまうことで、読み手としては混乱してしまうのですね。
全体が長くなっても、読みやすい文章があるならば、次のようなことを意識されているからです。
- 一文が短い
- 接続詞が適切
- 時系列に沿っている
文章の長さと丁寧さは比例しません。わかりにくい文章は不親切です。
接続詞が“不適切”というのはどういうことかというと…
果物が好き、だけど、たくさん食べた…というのは、おかしな日本語ですよね。
果物が好き、だから、たくさん食べた…なら、わかります。
ですので、接続詞が適切な文章にするならば、
です。
逆のことを言っているわけではないのに、「ですが、」を使う文章は書き言葉でも話し言葉でもよく見聞きします。
間違っていても誤解を与えるほどではないですが、やはり違和感があるので、ちょっとした負荷(ストレス)が脳にかかってしまうんですね。
書き言葉の表現をマスターしよう!


ビースマート話し方講座では、話し方だけでなく、書く力も磨けるように『ブログ添削』でサポート致します。
今、ブログを開設していない方でもOKですし、ブログではなく、コミュニティのレポートを添削させてもらったこともあります。
ブログという媒体にこだわらずに受けられるサポートメニューです。
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。



コメント